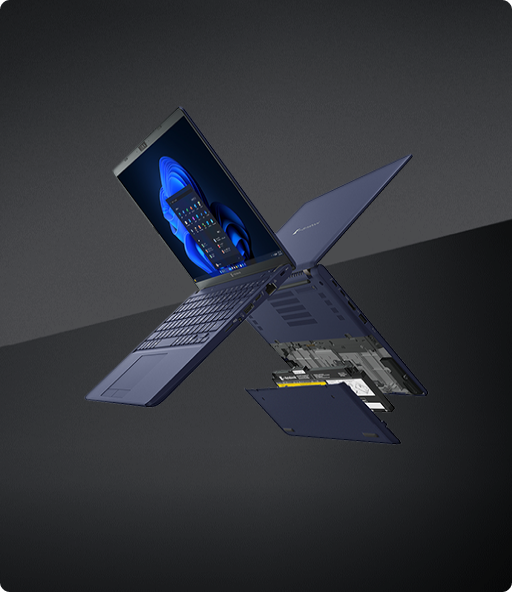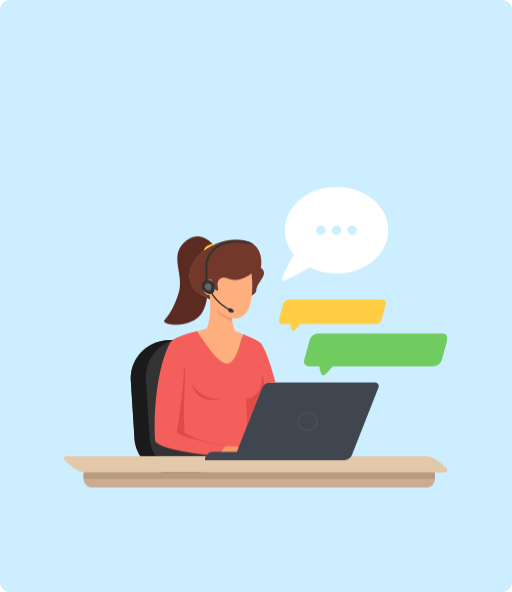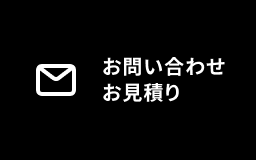クラウド型は、インターネット経由で生成AIの機能を利用するスタイルです。最大のメリットは導入スピードと拡張性。サービス提供事業者が用意した最新のAIモデルを即時に活用できるため、PoC(概念実証)や小規模導入にも適しています。
また、利用状況に応じてリソースを柔軟に増減できるため、急な利用拡大にも対応可能。月額課金型のため初期コストも抑えられ、特に中堅・中小企業にとって現実的な選択肢です。
-
クラウド型が向いているのは:
- • 導入を急いでいる企業
- • トライアル導入から始めたい場合
- • 社外連携を前提とした活用が多い業務
-
注意点:
一方で、外部サービスとの接続が前提となるため、秘密情報や個人情報の漏えいへの注意がオンプレミス型より重要となります。また、自社のセキュリティポリシーや業界規制との整合性に注意が必要です。ネットワーク環境に依存するため、安定性の確保も検討ポイントです。